5月13日(金)、「事業構想論Ⅰ」(担当教員:松本 祐一、履修人数:274名)の授業にゲスト講師として、株式会社IDEASS(所在地:東京都中央区)取締役 最上雄太様にご登壇いただきました。
同社は社会人向けの各種教育サービス、組織開発コンサルティングを事業とする会社です。知恵(ideas)の集まりでありたいという願いと、IDEASSの知恵によりお客様の「思い」を実現したいという企業理念を示しています。
講義では「事業構想を支える想い」をテーマに最上様の30年の歴史をお話しいただきました。30年の中で迷いながらも「常に自分に正直に生きる」ことを軸に行動し、MBA(経営学修士)取得・起業・博士学位(Ph.D.)を取得され、今なお挑戦し続けているとのことでした。
松本教授との対談では、「転職するときに次の職場を探す基準とは」「新しいビジネスを始めるときにまずは何から始めたのか」「研修事業という業種の中で唯一無二をつくるには」など具体的な起業のヒントを伺うことができました。
学生からは事業の今後の展開や「選択を決断する時に考えた事や基準があれば教えてほしい」などの質問がありました。
最後に「人生に起きるいくつもの選択は、経験に基づいて認識する流れを感じることや自分の軸と向き合うことで決定する」とお話がありました。
<株式会社IDEASSのホームページ>
http://www.ideass.jp/

最上雄太様
パネルディスカッションの様子

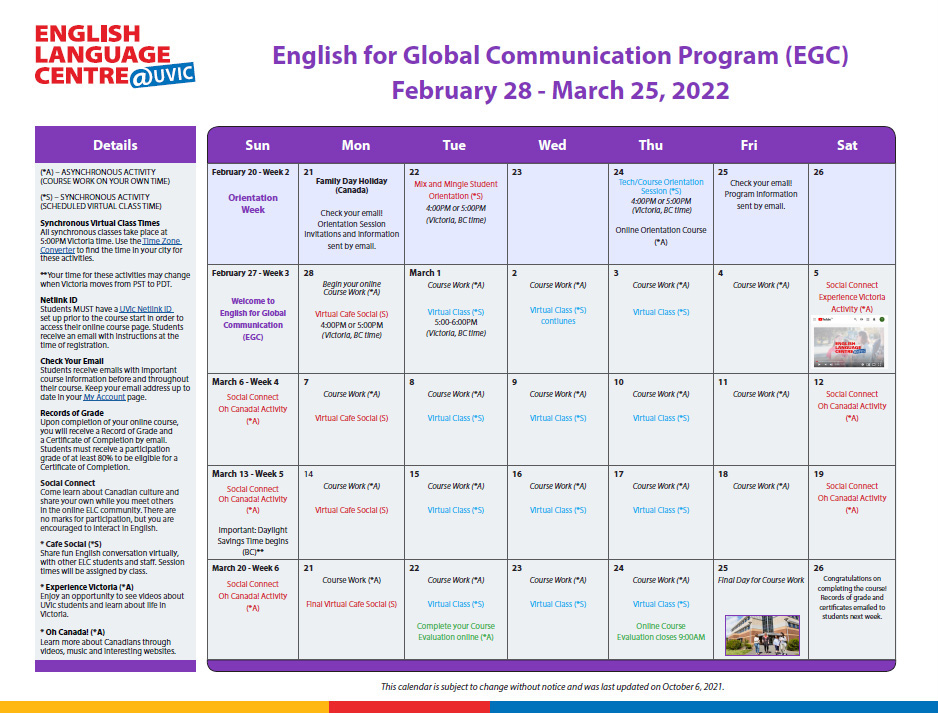
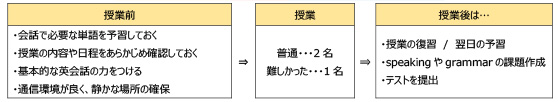




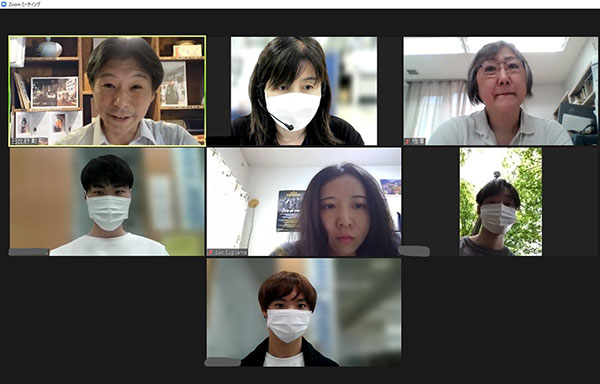
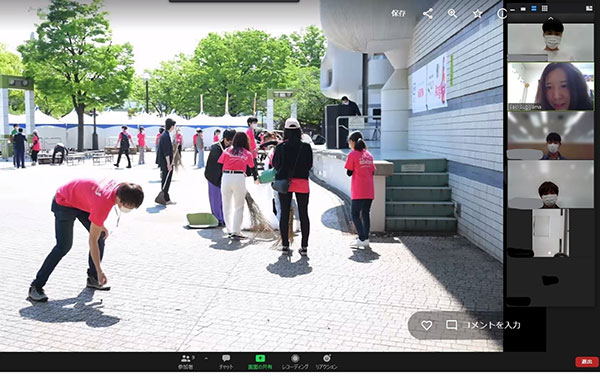





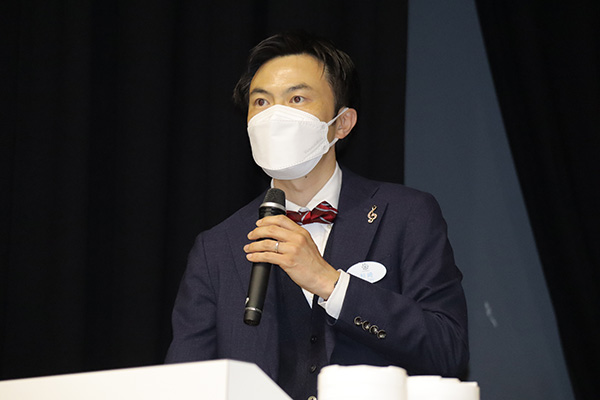








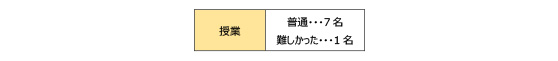








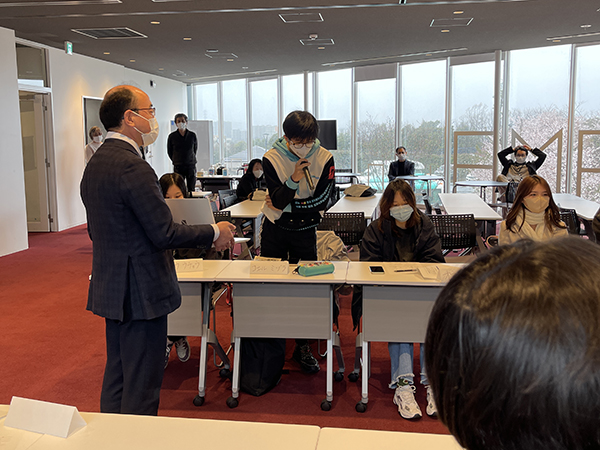


 説明会
説明会 杉山さん
杉山さん