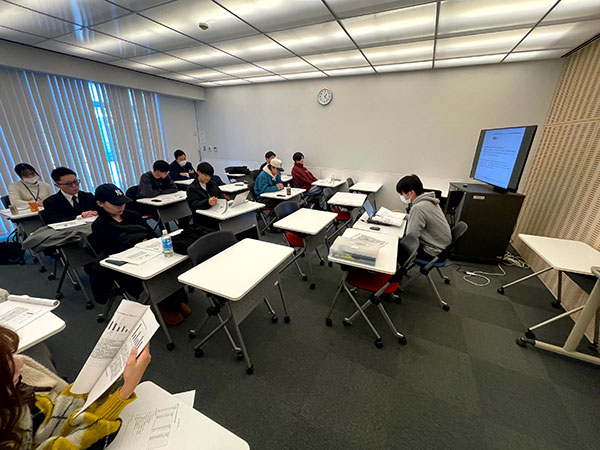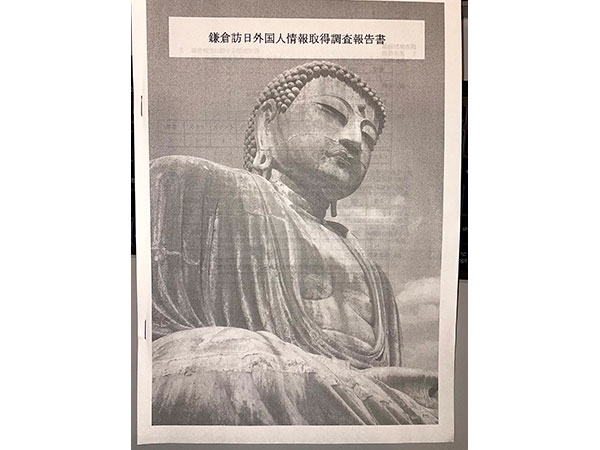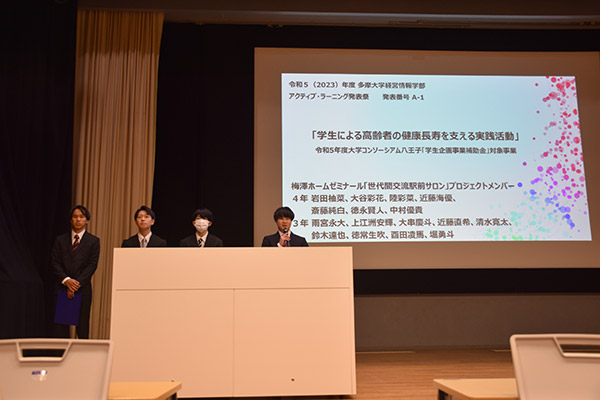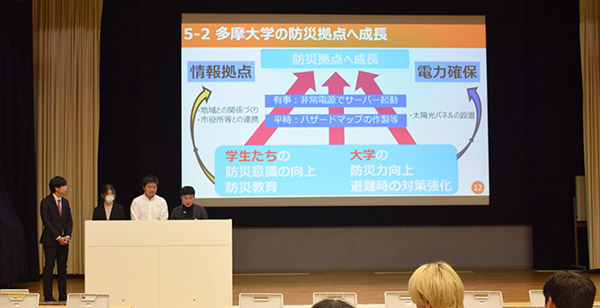【第3日曜日】第40回放送:1月21日(日)午前11時~
【第3日曜日】第40回放送:1月21日(日)午前11時~
番組の冒頭では、世界各地で選挙が行われる2024年の口火を切った1月13日の台湾総統選の結果をもとに、今後の米中関係や世界情勢の展望等について、寺島学長が分析します。
そして、今年の世界情勢を展望する上で鍵となる米国に焦点を当て、第2回・第3回の放送でも取りあげ、2020年の大統領選からあぶり出された「米国の分断」について、今年の大統領選を視界に入れながら、米国の政治・経済・民族・宗教などの視点を土台に、「分断」の本質的な構造と歴史的深層に、寺島学長がさらに踏み込んで語ります。
【第4日曜日】「対談篇 時代との対話」第32回放送:1月28日(日)午前11時~
<ゲスト>:真壁昭夫氏(多摩大学 特別招聘教授)、白井さゆり氏(慶應義塾大学総合政策学部 教授)
今回は経済及び金融の専門家・真壁氏と白井氏をゲストに迎え、2024年の世界経済・金融政策の展望と今後の課題等について、寺島学長と鼎談致します。
寺島学長の一人語りの第3日曜日(2020年10月放送開始)と対談篇の第4日曜日(2021年4月放送開始)は、YouTubeでの視聴総数が997万回を超え、まもなく1,000万回を迎えます。
地上波放送・エムキャスでの視聴総数もほぼ同数と、大変多くの視聴者に、世界の動きの本質を考える「座標軸」として番組を熱心にフォローして下さっており、日本国内・海外在住の幅広い年代層の方々にご視聴いただいております。
《メディア出演情報(一覧)》
■2024/1/21(日)11:00~11:55
TOKYO MX1 「寺島実郎の世界を知る力」 第40回
■2024/1/23(火)06:00頃~
TBS系ラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」 全国33局ネット
■2024/1/28(日)08:00~
TBS系列「サンデーモーニング」
■2024/1/28(日)11:00~11:55
TOKYO MX1 「寺島実郎の世界を知る力-対談篇 時代との対話」 第32回
■2024/2/11(日)08:00~
TBS系列「サンデーモーニング」
【TOKYO MX テレビ】
『寺島実郎の世界を知る力』、『寺島実郎の世界を知る力-対談篇-時代との対話』
<見逃し配信>
Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZ0Cdjz3KkhlIA30hZIT5Qnevsu0DBhY
エムキャス
(第3日曜日):https://mcas.jp/movie.html?id=749856148&genre=453017953
(第4日曜日[対談篇]):https://mcas.jp/movie.html?id=749856661&genre=453017953
*寺島文庫ウェブサイトからもアクセスできます。
https://www.terashima-bunko.com/minerva/tokyomx-2020.html