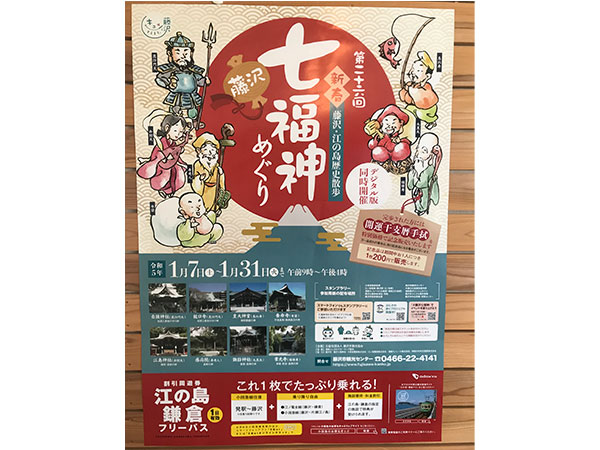秋学期から交換留学中の4年生の久保田眞司くんから留学報告が届きました!
タイのバンコクにある泰日工業大学(たいにちこうぎょうだいがく 英称:Thai-Nichi Institute of Technology 略称:TNI)へ出発して約2ヶ月。とても充実した日々を送っているようです。1学期間はあっという間に過ぎてしまうので、残りの滞在期間もより多くの経験を積んで帰ってきてくれることを願っています。
念願叶った留学(泰日工業大学)
久保田 眞司
■タイを留学先に選んだ理由
多摩大学の交換留学プログラムを通してタイに来てそろそろ2ヵ月になる。約4ヵ月間のタイへの留学渡航前、多くの友人にタイへ留学に行く予定だと伝えた際に「なぜタイを選んだのか」と沢山聞かれた。現地の生産業の現状を知りたい、物価が安いなどの理由はあったが、本当のところは「タイに呼ばれた気がした」からだ。留学自体は大学1年生の時から考えていた。当初はヨーロッパ圏に行くことを考えており、アジア圏は視野に入れていなかった。しかし、コロナウィルスの感染が拡大し、あらためて多くのことを考察する時間ができたときに他の学生とは違った場所に留学したいと強く感じた。留学先をどこにするか考えていたときに多摩大学院で教鞭をとられている田坂広志教授の書籍「直感を磨く」を拝読し多大なる感銘を受けたことをきっかけに、自身がふと「何か」を感じたタイへ留学することを決意した。そして何より、多摩大学グローバルスタディーズ学部の学部長である新美学部長から泰日大学への推薦をいただけたことも大きな理由だ。実際にタイに来てみて、本当にタイを留学先に選んで良かったと深く感じている。

■留学前の準備
タイへの渡航前に準備したことは大きく2つある。語学学習と留学ビザの取得準備だ。語学学習では英語を重点的に学習した。多摩大学の長期留学奨学金取得をモチベーションとして、TOEICと英会話力の向上に重点を置いた継続的な学習を行った。結果として、留学前にTOEIC公開テストで700点台後半の点数を取得することができ、無事に奨学金をいただくことができた。留学ビザの申請準備は多摩大学湘南キャンパス国際交流課のサポートのおかげでスムーズに学生ビザを取得することができた。加えて、タイの文化についても渡航前に少し学んだ。
■現地での生活
タイで過ごしてみて思うことは、タイでの生活は毎日が刺激と発見に満ちているということだ。それは例えるとすれば、毎日レジャーランドにいる気分だ。歩道をさも普通のように走るスクーター。逆走するスクーター。屋台をサイドにくっつけたスクーター。あってないもののような交通規則。インフラ設備も都心から離れるとまだ十分とは言えない。また外の気温が暑いため、室内はクーラーが良く効いており寒い。タイに来てからこの寒暖差のために体調を数回崩した。そうした体験に加えて、世界中から多くの人々が集まってくる。自身もこの2か月で10カ国以上の人々と繋がりを持つことができた。一国にいながら世界中の人々と関わりが持てるのは間違いなくタイの大きな魅力だ。そして感情表現が豊かなタイの人々と過ごす生活は日本では絶対に経験できない素晴らしい生活だと強く感じている。
■泰日大学での授業
現地の大学である泰日大学では自身が学んでいるGBM(Global Business Management)学部のウィパワディー学部長を始めとした教授の先生方が暖かく迎えてくださった。また、クラスメイトともタイ語会話本のおかげで比較的早く打ち解けることができた。そうして12月半ばには一緒に旅行に行くまでの仲になった。その他にも学内外で多くの友人ができた。GBM学部は英語でビジネスを学ぶカリキュラムが豊富で日々英語を活用する機会があり、とても良いと感じている。渡航前は英語を使う機会はあまりないのではないかと思っていたが、実際にタイに来てみて毎日英語を使う機会に恵まれている。そうした満足度の高い授業内容に加えて異なるバックグラウンドを持った相手と自分から積極的に関わる姿勢の大切さを学べたことは今後の人生において活かすことのできる貴重な経験だと強く感じた。

■ビザの更新
在日本タイ大使館で取得した学生ビザの有効期限は90日間しかなく、現地での更新が必要だったので、12月の終わりにバンコク内のイミグレーションでビザの更新手続きをした。月曜日の朝に行ったが、90人が待っていた。手続きが終わったころには午後17時になっていた。ビザの更新書類については、泰日大学に事前に申請を行っていたので特に問題はなかった。今後はオンラインからの予約もできるそうなので、今後のビザ更新はもう少し円滑に進むと思う。

■さいごに
今回タイに留学ができて本当に良かったと思う。現地に来てから環境の変化や気候の変化に慣れるまで少し大変ではあったが、こうした出来事も留学をしなければ味わえない醍醐味だと思う。短期間、長期間を問わず留学をすることはその後の人生にとって間違いなく大きな影響を与えることだと思う。自分もタイに来て本当に多くのことを経験することができた。英語があまりできなくても思いを伝えたいという気持ちがあれば相手も理解しようとしてくれる。最後に、留学に対して不安がある学生もいると思うが、「人生は一度きり」なので勇気を出して一歩を踏み出してほしいと思う。




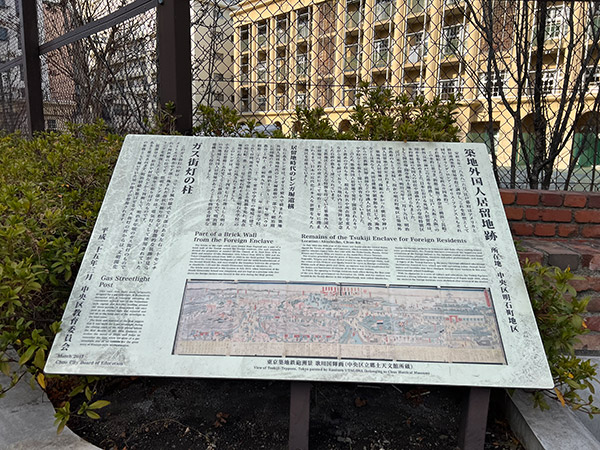



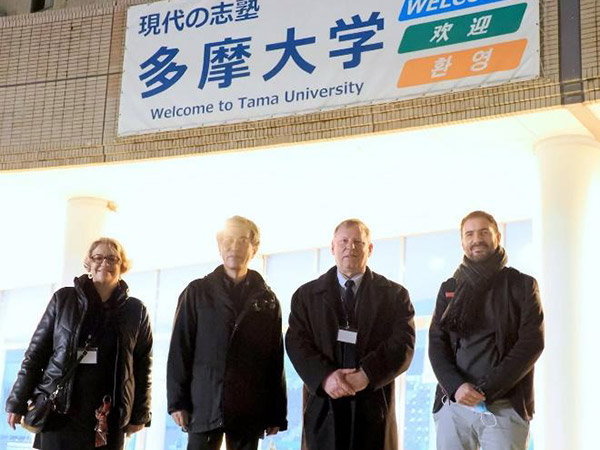
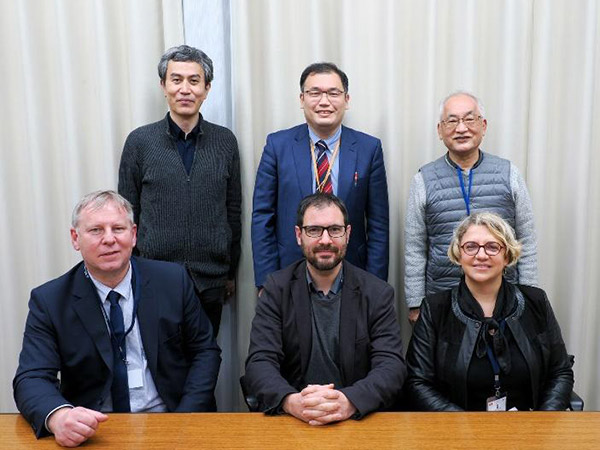

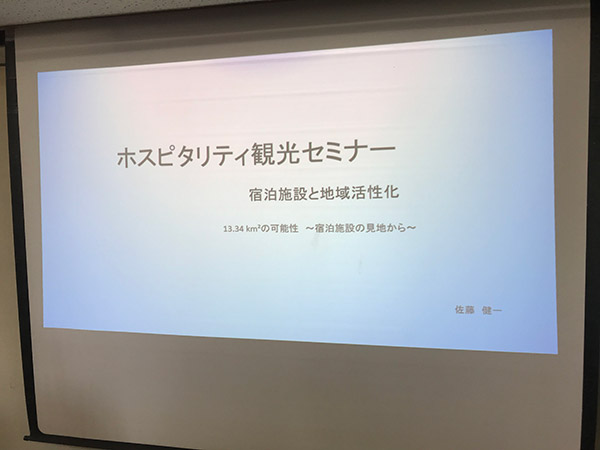
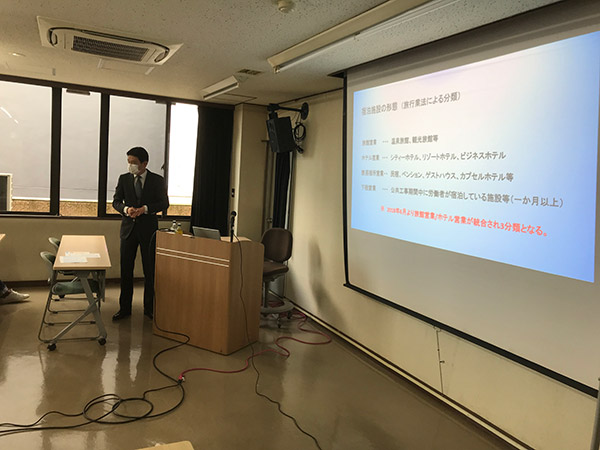









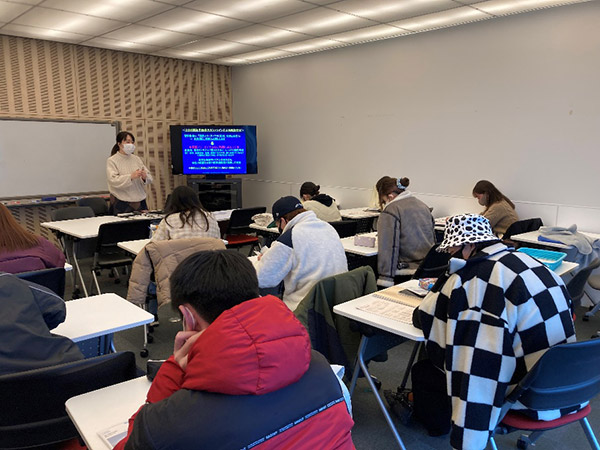





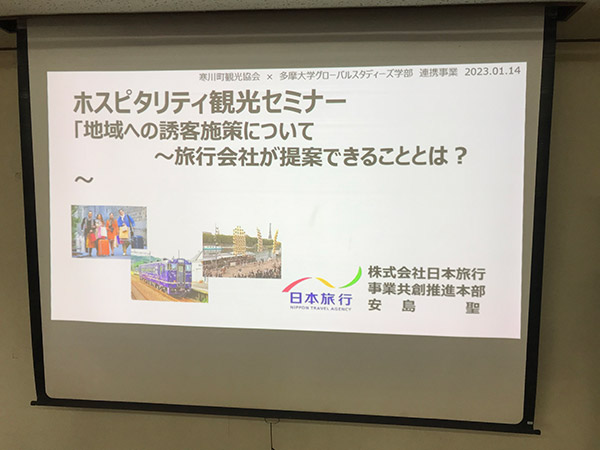
 株式会社日本旅行 地方創生推進本部チーフマネージャー
株式会社日本旅行 地方創生推進本部チーフマネージャー